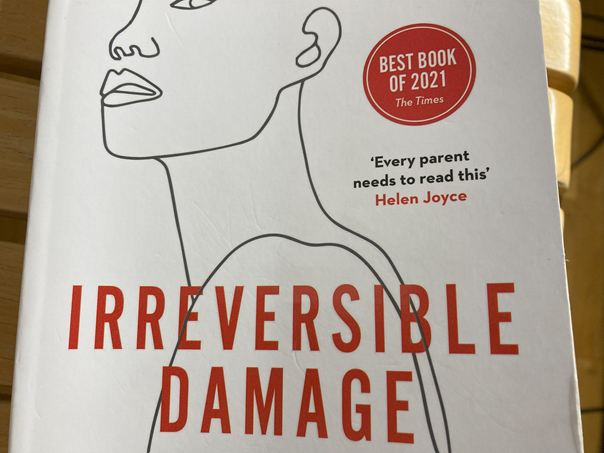マルコム・シユーネの『ウォークネス―事務方主義の最高の段階としての』を訳してみた。保守系シンクタンクのマンハッタン・インスティチュートが発行する雑誌『City Journal』の2022年春号に掲載されたコラム。
20世紀前半、アメリカの思想家であるジェームズ・バーナムは、専門化した経営者が資本家に代わって会社を支配するようになるだろうと予測した。すなわち、資本主義の後を継ぐのは社会主義者ではなく、ある種の職能集団であるということだ。ある意味、その予測は実現しつつある。ただし、シユーネによれば、新しく支配権を握ろうとしているのは経営者ではなくウォーキズムである。
マルコム・シユーネは1987年生まれのスウェーデンの評論家。本人はマルクス主義者であるとしているが、ポピュリズムに好意的であることから保守派であるとみなされることが多い。
タイトルの『Wokeness, the Highest Stage of Managerialism』(ウォークネス―事務方主義の最高の段階としての) は、レーニンの『帝国主義論』の英題『Imperialism, the Highest Stage of Capitalism』(帝国主義―資本主義の最高の段階としての) からインスピレーションを得たもの。
managerialism の訳は「事務方主義」とした。「経営者主義」では意味が違うし、「管理主義」では最も高いレベル (経営者など) からの管理のような印象を与えてしまう。民間の管理手法を自治体に持ち込むという意味で「マネジェリアリズム」という訳もあるようだが混同は避けたいし、カタカナ表記はできるなら使いたくない。「事務方主義」は聞いたことのない言葉だが、官僚による行き過ぎた支配が「官僚主義」と呼ばれるなら、事務方(ここでは、NPO/慈善団体、職場の多様性関連部署、SNSのキュレーション部署など、中位レベルの管理組織を指す)による行き過ぎた支配を「事務方主義」と呼んでもいいのではないかと考えた。また、バーナムの文脈では manager は「経営者」と訳す方がしっくりくると思うのだが、文章の中で統一するためにこれも「事務方」と訳した。
訳文中、[ ] は訳注、( ) は原文にある注を示す。
www.city-journal.org
(翻訳ここから)
ウォークネス―事務方主義の最高の段階としての
文: マルコム・シユーネ (Malcom Kyeyune)
公開: 2022年6月
最近の政治的な対立や文化戦争の対立がどれほど新しいものか忘れてしまいそうになるが、ほんの10年前、批判的人種理論はオンラインや学術的な場所でのみ目にするものだった。[米国]民主党の政治家は同性愛のカップルのシヴィル・ユニオンについて話していた[注1]。メディアや連邦政府は、過去の壊れた人種関係を修復するアメリカの試みがどれだけ成功しているかを言い募るのに忙しかった。今日、こうした古い秩序はほとんど残っていない。この変化はどれほどの速さで巻き起こったのだろうか。単純な尺度として、アメリカの四大新聞に「racism」(レイシズム)という単語が表れる頻度を見てみよう。1970年代から2010年まではほぼ横ばいだったその使用頻度は、2012年ごろを境に急激に高まった。その動きを牽引したのはワシントン・ポスト紙とNYタイムズ紙である。
注1: リベラルな政治家ですら正式な結婚ではなくシヴィル・パートナーシップについて議論していたということ。
この「グレート・アウェイクニング (偉大なる目覚め)」は、政治的な連合をひっかき回し、広く支持されていた真実を転覆させたが、ウォークネスそれ自体の概念はあいまいなままだ。ウォークネスは1つの信念体系(ライターのウェズリー・ヤンはこれを「後継イデオロギー」[注2]と名付けた)であるという当たり前の定義にもそれなりの価値がある(See “The Identity Cult,” Winter 2022.)。しかし、アメリカの二極化が進むにつれ、ウォークネスは社会的、経済的、法的、政治的な現象でもあることが明確になってきた。人々の頭の中にだけ存在する思想だと単純に考えるわけにはいかなくなったのである(See “The Genealogy of Woke Capital,” Autumn 2021.)。
注2: ウェズリー・ヤンによれば、後継イデオロギー (Successor ideology) とは、インターセクショナリティ、社会正義、アイデンティティ・ポリティクスなどを中心に据える米国左派の新しいイデオロギーを指す。
ウォークネスが制度的な力を持つものなら、その説明には比較分析が役に立つだろう。ほとんどの欧州人は、進歩的な西欧に比べてアメリカが古臭くて保守的だと思われていた頃のことを覚えている。それにもかかわらず、2022年の今、アメリカは他の西洋諸国に比べてより深刻な二極化と社会対立のさなかにある。世論調査によれば、公的機関への信頼は急速に失われている。二大政党のいずれかに自分を重ね合わせる米国人のうち、もう一方の党を民主主義への脅威だとみなす人々の割合は増えている。
では、私の母国である社会主義的なスウェーデンのような伝統的に進歩派の国に住む人々は、米国人と同じことを信じ、同じ本を読み、同じ考えを提唱しているのに、なぜ米国を苦しめている破滅的な社会の二極化を体験せずにすんでいるのか。アメリカの資本家が他の西側諸国よりもウォークに走ってしまったのはなぜなのか。アメリカでは、北欧諸国では考えられないような方法で大企業が直接的に政治闘争に介入している。こうした振る舞いが単純に新マルクス主義や社会主義といったイデオロギーの産物なのだとしたら、与党の社会民主党が今でも国会で「インターナショナル」を歌うスウェーデンのような国でこそ広がりを見せてもよさそうなものなのに。
ジェイムズ・バーナム[注3]が1841年に発表した『The Managerial Revolution』(注: 邦題は『経営者革命』)の中心的なテーマが、現在西洋で何が起きているかの理解を助けてくれる。この本において、元々はトロツキー主義者でありながら戦後アメリカの保守主義の中心人物となったバーナムは、西洋社会で資本主義が崩壊したり、社会主義に取って代わられたりすることはないだろうと論じた。そうではなく、アメリカの資本主義の後を継ぐのは社会主義ではない何かになる可能性が高いと彼は主張した。それは、古典的な意味で資本家が権勢を振るうようなものではなく、正式な所有権を持っていようがいまいが、事務方階級[注4]が現実の経済を支配するようなものになるという。
注3: James Burnham (1905-1980)はアメリカの哲学者、社会思想家。資本主義社会では資本家 (会社の所有者) が支配者であるが、将来的には専門化された経営者 (manager) が企業の新しい支配者になるだろうと主張した。
注4: バーナムが使う意味での manager はおそらく「経営者」と訳す方がしっくりくるのだが、この文章内での manager の訳を統一するために、ここでも「事務方」と訳すことにする。
資本の所有と資本の支配の違いは、戦間期 [注: 第一次世界大戦と第二次世界大戦の間]にも議論の的となったことがあった。その初期の分析では、ソ連の共産党政治局員が公的資源を支配する権限を占有していたと指摘された。米国では、バーナムによる新しい事務方秩序の予言は、ニュー・ディール政策を背景として生まれたものだ。そしてこれは、資本主義的な考えへの疑念が高まった時期に重なっている(それはある程度は理解できることだ)。パワー・バランスは、財産権から、着実に拡大を続ける人権へと移りつつあり、米国人は国家が計画および管理する社会領域が拡大していくことに抵抗をなくしていった。
バーナムは、1940年代前半のアメリカがどこか一過性の段階にあると見ていた。旧来の資本主義秩序は明らかに病んでいて、事務方がオーナーの代わりに着実に力を伸ばしている。だが、新しい支配階層を形作るプロセスはまだ完了していない。いたるところで生産手段を支配する権限が事務方に移行しつつあるけれども、「強大な力を持つブルジョワジーと金融資本家が今でも米国の支配階級であることに変わりはない」とバーナムは書いている。ニューディール主義は資本主義に完全に置き換わることのできる「成熟し、体系化された事務方イデオロギー」ではまだなかった。
しまし、バーナムが今でも生きていれば、ウォークネスをまさしくそうしたものだと捕えたかもしれない。すなわち、新しい事務方階級を代表して、それ自体で社会を支配する権利を主張できる体系化された事務方イデオロギーである。戦間期やニューディール時代にバーナムのような思想家を悩ませ、または魅了したダイナミズムの多くが、肥大した形で今日また現れているようなのである。
所有権と支配の話に戻ろう。実業界で発生した数多くの論争を見てもわかるように、ウォークネスは財産権をはく奪する働きをしている。最近マイクロソフト社に買収された巨大ゲーム会社のアクティヴィジョン・ブリザード社の運命について考えてみよう。何人もの元社員が、同社のカリフォルニア・オフィスにおけるハラスメントと男子学生社交クラブ的文化について告発の声をあげた。それを受けて、同社はさまざまな方向から攻撃を受けた。まず、カリフォルニア州が同社を告訴した。次に、メディアが熱心に報じ始めた。さまざまなNGOと活動家組織がこの論争に飛びつき、証券取引委員会は調査を開始した。同社に対する元々の告発は職場でのセクハラに関するもののみだったが、アクティヴィジョン・ブリザード社に突きつけられた要求のリストはすぐに最初の罪を超えたものに伸びた。問題を起こした社員を解雇して単に職場改革を実施しただけではすまなかった。アクティヴィジョン・ブリザード社は、さまざまな”多様性”の目標基準を満たすために、社内的な採用・解雇の意思決定をある種のパブリック・レビューに委ねなければならなくなった。この論争の行間を読み取れば、会社のオーナーがその雇用プロセスを他の事務方機関にレビューしてもらわなければならなくなったことは明らかである。
ウォークネスが社会に課す主要な実務的要求は、以前は独立していた社会的プロセスと経済的プロセスに事務方が介入できる範囲を大幅に拡大することである。アクティヴィジョン・ブリザードについて言えば、職場環境に関する論争が、従来のものに取って代わる新しい人事の仕組みを実行に移すための戦いとなった。この新しい人事の仕組みには会社の経営陣のコントロールが及ばず、また会社はそれに対してある種のイデオロギー的みかじめ料を支払わなければならない。これが実質的に意味するところは、些細とは言い難い財産権の放棄である。あなたは会社のオーナーかもしれない。しかし、外部の審査委員会の“助け”を借りることなく、思いどおりに会社を経営できると思ったら大間違いだ。忍び寄る介入の例をもう1つあげよう。いわゆる人種的公正コンサルタントを雇用するというハリウッドのトレンドである。映画やテレビドラマにさまざまなマイノリティ出自の俳優が適正に起用されていることを確認するコンサルタントである。かつての脚本家は、感情移入や想像力といった生々しくて公正さとは無関係な手段を活用して、プロットを構成し、登場人物を肉付けしていた。こうした手法はますます許されなくなってきている。さまざまなマイノリティ出自の登場人物をシナリオに含めることが奨励されているだけでなく要求されているのである。それも、仲裁的コンサルタントを依頼した上で行わなければならない。今や物を書くにも道徳的事務方階級の介入が必要とされるのである。
こうして見ると、ウォークネスは単なる学問的なイデオロギーではない。実際のところ、ウォークな人々は彼らの想定についてソクラテス式問答を行うことには興味を示さない傾向がある。2017年、フェミニスト哲学誌の『ハイパティア』は大規模な論争に巻き込まれた。ライターのレベッカ・テュヴェルが、トランスレイシャリズム[注5]もトランスジェンダリズムと同様の哲学的地位を与えられるべきだと論ずる記事を発表したのである。テュヴェルは社会的カテゴリを乗り越える人々の哲学的な意味を探るために真摯な議論をしているようであったが、その取り組みにより彼女はつまはじき者となった。
注5: たとえば生物学的に白人であっても、その人が黒人であると自認しているのであれば黒人であるとする考え方。
ウォーク・イデオロギーは学術的な議論にはほとんど役に立たないかもしれないが、組織に対する支配を確立するのにはかなり長けている。ウォークな論争を組織内の採用・解雇の特権に関する闘争と分けて考えることは不可能だ。原理に関する闘争のようにも見えるが、それは同時に制度的な特権と資源へのアクセスに関する闘争でもあるのだ。
バーナムが予期した事務方イデオロギーと同じように、ウォークネスは所有権に優先されるさまざまな権利を主張し、こうした権利の実現を監視するための恒久的な事務方階層の創出を要求する。介入の傾向は現代社会のほぼすべての側面に及ぶ。そこには、かつては政治システムの基礎をなすとみなされていた分野も含まれる。たとえば、民主主義が適切に機能するには、さまざまな形の介入が必要であると考えられるようになった。事務方の関与がなければ、一般大衆のむき出しの表出が逸脱行為、たとえばドナルド・トランプの選出やEUを離脱するという英国の決定につながるというのである。暗愚に違いない有権者にどの政治的質問や問題の決定権をまかせてもOKなのか。それを判断する専門家の存在を必須のものにしようとする声は大きくなるばかりだ。
専門家の指導に頼ることで、議論の分かれる問題を公開の討論の俎上に載せないようにしたいという強い衝動は、さまざまな形をとって現れている。たとえば、エクスティンクション・レベリオンだ。これは、ごく一部で高い支持を持つにすぎない急進的な環境団体だ。だが、彼らが壊れていると信じる政治体制を、こうした考えに沿って修正するためのビジョンを明確に打ち出している。エクスティンクション・レベリオンが構想するのは “市民議会”の導入だ。この市民議会は、市民の代表者からなる“ミニ公衆”によって構成される。このミニ公衆は専門家階級が選択した情報を受け取り、それに基づいてさまざまな推薦事項を練り上げる。専門家は、ミニ公衆の(拘束力のない)推奨事項に耳を傾けた後、何が最善かについて意思決定を下す。
しかし、なぜアメリカはヨーロッパ諸国よりウォーク化が進んだのだろうか。同性婚など進歩主義イデオロギーの政策の多くは、欧州ではアメリカよりも早く達成されており、また、ヨーロッパ大陸と北アメリカ大陸はよく似た考え方を共有しているのに。
私の考えでは、この状況の原因の1つは、アメリカの事務方階級が持つ物欲的な不安感である。ピーター・ターチン[注6]が主張するように、事務方階級に属する人の数が増えすぎたため、彼らの高い経済的期待を満たすような形で彼らを社会に吸収することができなくなったのだ。たとえば、米国に比べてスウェーデンにおける二極化の進行ははるかに遅く、文化的な環境もかなり穏やかである。スウェーデンでは、事務方階級の子弟たちにあらゆる種類の仕事を提供するために、巨大な政府機構を動かしている。私の住むウプサラはネバダ州リノの3分の2の規模の市だが、100人近くの「コミュニケーター」を雇っている。彼らの公式な仕事のほとんどを占めるのは、市のソーシャル・メディアのアカウントを管理することと、政策文書を書くことである。コミュニケーション部局は機能不全に陥っていることで悪い意味で有名である。市は、これらのスタッフが1日中何をしているのか調べるために外部のコンサルタントを雇った。しかし、少なくともある意味では、コミュニケーション部局はやるべきことをやっていた。それはすなわち、この職に就いていなければ失業者となり、社会的な扇動者になりかねなかった大学卒業生に不要不急の仕事を提供したのである。
注6: Peter Turchin (1957-) は歴史動態を数学的にモデル化することを専門とする複雑系科学者。
スウェーデンには、さまざまな税金、民間委託、手数料、その他の便宜があふれている。それらすべてが合わさって、アーティスト、役人、ジェンダー学専攻の大卒者、活動家、学芸員、マインドフルネス・コンサルタント、環境保護推進者などを雇用する巨大なパトロン機関ができあがっている。同国政府は芸術、教育、NGO、そしてジャーナリズムにまで気前よく金を出している。スウェーデンの主要紙のほとんどは、助成金がなければ黒字経営ができない。スウェーデンの政治経済を最もよく表しているのは、スウェーデン人は1ガロンのガソリンに対して約9ドルを支払っているという事実である[注: アメリカでは約3.5ドル]。ガソリン代がこれほど大きく違う原因は、社会事業に必要な資金を生み出すための税金や手数料にほぼ帰することができる。ガソリン税が導入された当初の目的は、主に道路維持費を賄うためだった。今では人々は環境問題に対処する資金を捻出するためのガソリン税を上げるべきだと議論している。こうした環境問題に携わる事務方は、ブルーカラーの地方在住者に逆累進の税金を課すことで自分たちに資金が回ってくるように企てている。
これは注目に値することだが、スウェーデンではカール・リンネの記念碑を取り壊す計画はない。偶像破壊と像の引き倒しの熱狂がアメリカを席巻していたときですら、スウェーデンの活動家は像の除去についてオンライン投票を行い、過半数の支持が得られないとわかるとそれをあきらめることでよしとした。像の引き倒しは、それを所有する市が自分の雇用主になる可能性が高い場合にはそれほど魅力的ではないのである。
もともとはこの目的を念頭に設計されたものではなかったとしても、一般的にヨーロッパの社会民主主義福祉国家は大卒で野心のある事務方階級に新しい形の福祉を提供するようになった。労働者と資本家の間の格差を取り除くことが当初の目的だった積極的な租税政策は改変され、地方の小規模事業主や労働者に最もひどい打撃を与え、快適な都会に住む人々にさまざまな助成金や税の優遇を提供するものになった。環境保護主義は、社会への介入が増大し続けることに対するもっともらしい言い訳を都市生活者に提供した。環境問題を重視する欧州の政党の支持基盤のほとんどが、都市に住む裕福な高学歴者で構成されていることは偶然ではないのである。
これとは対照的に、米国では公共部門の閑職が存在しないわけではないものの、人を遊ばせないでおくためだけの無意味な仕事の広まりが文化として根付くとは思えない。それは、深く染みついた文化的な通念にもその他の実務的な見解にも反するからである。米国の社会保障制度の範囲はより狭い(ただし、米国の社会保障制度は常に実際より低く評価されてきたし、欧州の社会保障制度よりも再分配指向であるのは事実である)。さらに、米国はより連邦主義的である。すなわち、ある人口集団から別の人口集団にリソースを移すような国家主導の大規模なプロジェクトの実行がより難しいのである。欧州では、経済における事務方の支配的立場は、責任ある福祉国家の自然な帰結として正当化されうる。欧州のウォーク派は、追いはぎに身を落とすことはほとんどない。事務方の取り組みに資金が必要なら、ガソリン税を上げるように求めればいいだけなのである。米国では、ウォークな事務方の介入は民間の企業や組織への強請(ゆす)りに似ている。
事務方社会の未来はどうなるのだろうか。[米国に追随する]欧州の動きは今後も衰えることがないのだろうか。米国は、その比類なき独自性を捨て、憲法の意図するところを乗り越え、徴税、あるいはおそらくは貢物の取り立てとでもいうものによって、事務方国家を拡張する資金獲得のための統一制度を生み出すだろうか。
おそらくそうはならないだろう。ヨーロッパでは、福祉国家への幻滅が広がる中で、事務方は反発に直面している。逆累進の税金が燃料価格の高騰に対する抗議活動に火をつけた。スウェーデン、フィンランド、アイルランド、そして最も激しかったのがフランスだ。今後数年間で、階級間や政治的陣営間での大規模な対立をヨーロッパが回避できる理由は特にない。それどころか、黄色いベストの反乱は欧州諸国に広がりつつある動きを前もって示したことになるだろう。
一方、米国とカナダでは、大きな労働組合の管理構造の傘に入っていない労働者は、専門家による介入に抵抗を始めているようだ。左派は常にこう教えられてきた。高い教育を受けた前衛のリーダーシップと組織を失えば、労働者は自分たちの声を届けることのできないのろまな木偶の坊(でくのぼう)に退化してしまうと。だが、これが間違いであることは証明された。今後は、労働者にさらなる制限を課そうとする事務方と労働者との間で対立が激化することは間違いない。
資本のオーナーに関してはどうだろうか。小規模事業主は反動の忠実な培養器であり、常に勤労者の反対側につくという極左の古い思い込みは、今後数年間で否定されるかもしれない。下級の資本家に関していえば、事務方体制はたいした褒美を用意できないばかりか、増殖する事務管理職階級の飽くなき要求により維持不可能な財務的負担が彼らに課されることになるだろう。また、アクティヴィジョン・ブリザード社の悲惨な運命は、非常に大きな企業ですらも、資本家と事務方が必ずしも幸せな共生関係を築けるわけではないことを示している。その関係は、対立と寄生にますます特徴づけられるものとなっているのである。
要するに、ウォークな事務方は新しい政治的・社会的秩序を強要したいと考えているのだ。事務方主義は介入を必要とする。そして、介入には正当化されたイデオロギーが必要だ。ウォークネスは、ニューディール主義が1940年代にけっして試みようとしなかったことを達成した。すなわち、制度的な破壊と過剰な権限拡大のほぼすべての行為を正当化できる、包括的で、柔軟で、冷酷なイデオロギーとなったのだ。しかし、ひび割れは既に現れはじめている。ガソリンの値段が高騰し、インフレーションが猛威を奮う今、事務方主義に内在する矛盾は激しくなるばかりだろう。ウォークネスがほんとうに100年近く前にバーナムが予期した事務方主義の (レーニンの言葉を借りれば)「最高の段階」であるなら、革命家でなくても次のような質問を思いつく。それはどれほど長続きするのであろうか、と。
(翻訳ここまで)
時事ニュース 人気ブログランキング - ニュースブログ