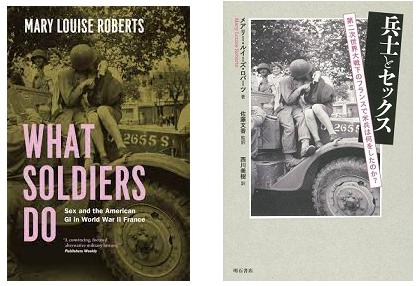今年の4月から米国HBO MaxでTVドラマ『Tokyo Vice』(トウキョウ バイス)が放映された。舞台は1999年の東京。主人公は、ヤクザなどが蠢く日本のアンダーグラウンド社会に足を踏み入れたアメリカ人新聞記者だ。主演はアンセル・エルゴートで、渡辺謙や菊地凛子が脇を固める。
原作となる同名の回想録を書いたのはジェイク・エーデルスタインだ。来日後に上智大学で日本文学を学び、1992年に欧米人として初めて読売新聞の社員となり、12年間勤務した男である。
ドラマ『Tokyo Vice』のレビューはおおむね好評だ。映画評論サイトの Rotten Tomatoes によれば、平均評価点は10点中7.6点。同サイトの評論家コンセンサスにはこう書かれている。「『Tokyo Vice』で最も興味をそそらない要素は主人公である。だが、日本のアンダーワールドの複雑怪奇さとその背景の迫真性により、魅力的なネオ・ノワールに仕上がっている」。
さて、ドラマの成功とは裏腹に、原作の『Tokyo Vice』には以前からよくない噂が付きまとっていた。作者のジェイク・エーデルスタインはこの本に書かれていることはすべて実際に起きたことだと主張しているのだが(注)、そんな荒唐無稽な話が本当であるはずがないと疑問視する声があがっていたのだ。インターネットでは彼を揶揄して「ジェイク・ザ・フェイク」(いかさま野郎のジェイク)と呼ぶ人もいる。
注: 情報提供者の保護のために名前と国籍は変更したとしている。
今年の4月、『Tokyo Vice』の放映開始に合わせて、米国のハリウッド・リポーター誌が彼に取材し、「『Tokyo Vice』の原作を事情通がこき下ろす」という記事を公開した。つまり、ドラマの下敷きとなったエーデルスタインの回想録には真実性が欠けているのではないかというのだ。おもしろい記事だったのでここに要約して紹介したい。
執筆したガヴィン・J・ブレア記者は、2009年に日本外国特派員協会で開かれたエーデルスタインの記者会見に出席して同協会の会報誌に記事を書き、2013年には『Tokyo Vice』の映画化の可能性についてハリウッド・リポーター誌に寄稿したこともある(映画化は実現しなかった)。
今回翻訳する記事が同誌で最初に公開されたのは2022年4月27日。オンライン版の記事ではその後いくつか追記がなされているようである。
(記事の要約ここから)
『Tokyo Vice』の原作を事情通がこき下ろす
2001年、後藤組の組長であった後藤忠政らは肝臓移植の手術を行うために渡米した。後藤は手術を行った病院に多額の寄付を行ったほか、入国を認めてもらうために連邦捜査局との間で山口組の内部情報を提供するなどの取引を行った。
後藤組は暴力団の不文律 (一般人を不必要に傷つけないなど) を無視することで知られる存在だったが、エーデルスタインはリスクを冒して記事を書き、その成功によって日本の闇社会にひるむことなく立ち向かうジャーナリストとしての評価を確立した。
読売新聞を退社後、エーデルスタインはデイリー・ビーストやLAタイムズなどに寄稿するフリーランス・ジャーナリストとなり、本も何冊か書いた。もっとも有名なのが2009年に出版された『Tokyo Vice』である。しかし、ノンフィクションとされるこの作品の真実性には長く疑問の目が向けられてきた。
エーデルスタインはほんとうに合気道の技を使って巨体の用心棒を倒したのか? ヤクザのスナイパーにつけ狙われたのか? 「私と寝たら情報をわたしてあげる」と女に迫られたのか? 女に札束を投げつけられて性的な奉仕を要求されたのか?
2022年4月の上旬、ハリウッド・リポーター誌の記者は六本木ヒルズでエーデルスタインにインタビューした。彼の回想録につきまとう疑問点について確認するためだ。エーデルスタインは魅力的な話し手だったが、2時間にわたる対話の中で話の辻褄が合わなくなることもあった。
エーデルスタインは、本の内容について「なんの誇張もしてない。起こったことをすべて起こったとおりに書いた」と主張した (ただし、暴力団の報復を避けるために登場人物の名前や国籍は変えてあるとしている)。
ドラマ『Tokyo Vice』のプロデューサーであるジョン・レッシャー (映画『バードマン』でアカデミー賞を受賞) は、エーデルスタインの本の真実性に関してこう語っている。「彼の本はドラマにインスピレーションを与えてくれたに過ぎない。ドラマ独自の設定も数多く追加されている。本の内容が本当かどうかは、エーデルスタイン本人や登場人物に聞くべきだろう。私はその場にいなかったのだ」。
本にもドラマにも、洒落たスーツを着こなすフランスびいきの同僚記者が登場するが、これはエーデルスタインと同時に読売新聞浦和支局に配属された辻井南青紀(つじいなおき)がモデルになっている。本では彼のニックネームは「フレンチー」、ドラマでは「タンタン」だ。
現在は小説家となり、京都芸術大学で教鞭も執る辻井は、「誰も私のことをフレンチーとは呼ばなかったし、新聞記者はみんな特徴のないスーツを着ていた」と語る。
辻井は長時間にわたるビデオ電話と2本のメールでエーデルスタインに対する賞賛の気持ちと好意を強調した。「後藤組について書くのは彼にとって危険なことだった。ほとんどの日本人ジャーナリストは、脅迫を受けたらあきらめていただろう」。
しかし、辻井はジャーナリストとして働いた経験があり、現在は小説家であるだけでなく小説について教える立場だ。ジャーナリズムと創作の違いを理解しているのである。
「日本はシステムに従って働く国だ。あの本の内容の一部は、書かれたとおりに起こったのではないだろう。まちがいなく誇張はある。だが、そこがジェイクの持ち味だ」。
エーデルスタインの回想録の最初の方に、読売新聞で働き始めた年の忘年会で彼と彼の同僚が大立ち回りを演じたという記述がある。その忘年会に出席していた辻井はそんな喧嘩を見た記憶がないという。
(記事の公開後、「その年の忘年会には出席してたというのは記憶間違いで、実際は出席しなかった」というメールが辻井から届いた)
エーデルスタインは、今回のインタビューでも、こうした喧嘩はしょっちゅう起こっていたと語った。「私たちの忘年会は暴力的だった。読売は軍隊のようだった。体育会のメンタリティを持っている人間がたくさんいた」。
また、記者一年生のエーデルスタインは、上司の許可を得て殺人容疑者の友人のイラン人に扮し、おとり取材を行ったという。
「読売の記者がおとり取材を許されるなどということは絶対にない。そんなことを上司に頼みもしないだろう」と辻井は言う。「日本では警察すらおとり捜査を行わない。最近少し法律が変わったけれども、おとり捜査は非合法で、そんな方法で証拠を集めることはできない。読売はそうしたことには非常に厳しかった」。
(記事の公開後、「ジェイクがおとり取材を行ったかどうかについて真実性を否定したわけではない」というメールが辻井から届いた)
エーデルスタインは、おとり取材の話は本当だという。「情報を得るにあたってルールなどなかった。情報を買う以外はなんでも許された」。しかし、その後の質問にはこう答えている。「行動規範やジャーナリズム精神について書かれた小冊子があって、読売はそれをバカみたいに真剣にとらえていた」。
『Tokyo Vice』の本の冒頭に、後藤組の仕事人が面とむかってエーデルスタインを脅迫するシーンがある。「記事を消せ。さもなくばお前が消されるだろう。おそらくお前の家族や友人も」。
このときエーデルスタインのそばには刑事がいたのである(ドラマでは渡辺謙が演じている)。刑事の面前でヤクザがそんなことを言うだろうか。この疑問について彼はこう答える。「ちょっと違う言い方だったかもしれない。『記事が消えるか、何か別のものが消えるか。お前にも家族がいるだろう? 』みたいな」。
彼の回想録によれば、2008年5月から5年間、彼は警視庁の保護下にあったという。後藤組の襲撃から身を守るためだ。しかし、この期間中、彼が命を狙われているにしては派手な暮らしをしていたことを多くの人が目撃している。
2009年11月、CBSの『60ミニッツ』という番組でエーデルスタインはインタビューを受けた。「生き延びるために何をしたのか」という質問に彼はこう答えている。「部屋のシャッターを下ろしたままにしておく必要がある。どこかの建物からスナイパーが狙っているかもしれないからね」。
ヤクザが使う凶器は一般的に刃物かピストルだ。ヤクザがスナイパーを雇ったという話は聞いたことがない。この事実をハリウッド・リポーター誌の記者に突きつけられたエーデルスタインは、最初はスナイパーの話をした事実を否定した。しかし、すぐに冗談を言っただけだと話を変えた。「こんな話を真剣に受け取る人がいるなんて思わなかったよ」。
エーデルスタインは、匿名の情報源から得たとする一風変わった話をニュース記事によく引用する。これについては東京在住の外国人記者などさまざまな人が首をかしげてきた。引用されるのは、ヤクザ、警察、政治家、公務員、一般人などの発言だ。ハリウッド・リポーター誌の記者は、エーデルスタインがLAタイムズ、アジア・タイムズ、デイリー・テレグラフ、フォーブス、アトランティック、そしてアジア・パシフィック・ジャーナルに書いた記事の中から、こうした引用が含まれるものを25本選び、彼に質問を投げかけた。
インタビューの最後に、エーデルスタインは記者を自宅に招待する。3日後に来てくれれば、匿名の情報源の存在を検証できるように、取材メモやその他の資料を用意しておくというのだ。しかし、翌日、彼からメールが届く。準備に時間がかかるので日程を2週間後にずらしてほしい。そして、弁護士が作った機密保持契約に署名してほしい、という。最終的に、自宅訪問の約束は当日、直前になってキャンセルされた。
(4月20日、ハリウッド・リポーター誌の親会社の上級役員にエーデルスタインからメッセージが届いた。「日本では、警官や公務員が記者に機密情報を漏らすと公務員法に違反することになる。私の良心として、情報源をシェアすることはできない」)
エーデルスタインの情報源からはときどき思いもよらない言葉が飛び出してくる。たとえば、デイリー・ビーストで2014年3月に公開された記事には、上納金を納めなければならないのに脅迫するときに暴力団の名前を使えないとこぼすヤクザが出てくる。「マクドナルドの店舗を運営するのに、ゴールデンアーチ (マクドナルドのロゴ) を使えないなんてことがあるかね」。同様のセリフは、2015年のジャパン・タイムズの記事にも、2017年4月のワシントン・ポストの記事にも出てくる。見たところ、異なる2人のヤクザが同じ表現を使っているようなのである。
エーデルスタインのヤクザ関連の功績や人脈についての疑念は、早くも2010年に出てきている。ナショナル・ジオグラフィックが『東京の犯罪の親玉たち』(Crime Lords of Tokyo) というドキュメンタリーのために彼をコンサルタント兼フィクサーとして雇ったときのことだ。ディレクター兼プロデューサーのフィリップ・デイは、エーデルスタイン自身や、『Tokyo Vice』に繰り返し登場する個性豊かな人々に会えることを楽しみにしていた。
しかし、制作チームは、東京に着く前からエーデルスタインについて疑念を抱き始めていた。彼が電話をかけてきて、「町でヤクザに電話帳で殴られた」と言うのだ。「その口ぶりからして、彼が本当のことを言っているとは到底思えなかった」とデイは述懐する。
プロデューサーのカルダー・グリーンウッドはエーデルスタインの第一印象についてこう話す。「彼の服装や物腰はだらしなくてがさつだった。カリスマ性などまったくなかった。現実のエーデルスタインは本に描かれたヒーローとはかけ離れた存在だった」。
仕事に直結することについて言えば、ナショナル・ジオグラフィックの制作チームは、彼らが期待しているヤクザの人脈などエーデルスタインは実は持っていないのではないかと疑うようになる。
デイによれば、エーデルスタインの戦略はこうだった。まず、ヤクザの周辺人物の何人かに会ってインタビューする。そこから、最終的に年老いた元ヤクザにつなげてもらうのだ。この元ヤクザという男は、一時期エーデルスタインの運転手として働いていた男だという(エーデルスタインによれば用心の役割も担っていた)。しかし、この男が足を洗ったのはかなり前のことであり、制作チームが番組の中心に据える「犯罪世界のインサイダー」には程遠かった。
制作チームとエーデルスタインの間にひびが入り始める。エーデルスタインは3週間の撮影スケジュールの半ばで突然、娘の誕生日があるから米国に行かないといけないと言い出す。「願ってもないことだったよ」とデイは言う。制作チームはすぐに別のフィクサーを雇って撮影を続けた。
新しいフィクサーの助けを得て、制作チームは3人の現役ヤクザ (2人の兄弟と1人の大物ヤクザ) との接触に成功する。元ヤクザの僧侶やヤクザに誘拐されたことのある女性の話を聞くこともできた。
米国から戻ってきたエーデルスタインは、番組の進捗状況に喜ぶどころか、激怒したという。デイはこう言う。「次に何が起こったかというと、ナショナル・ジオグラフィック経由で聞いたのだが、エーデルスタインはフォックス (当時のナショナル・ジオグラフィックの親会社) に連絡して、私たちがインタビューしたヤクザの兄弟が夜中にやってきて彼を殺すと脅したと言ったらしい 。私は一瞬たりともそんな話を信じなかったね。一瞬たりともだ。たわ言を言うなと私は彼に言った。彼はそれを面白く思わなかったようだね」。
それがきっかけとなって (とデイは考えている)、エーデルスタインはコロンビア特別区でナショナル・ジオグラフィックを訴えた。
訴状によれば、番組が放送されれば、エーデルスタインと番組に登場した人々の命が危険にさらされるという。また、番組がインタビューしたヤクザが出演の同意を取り消したという。エーデルスタインは、番組のスタッフとして働くことには同意したが、ヤクザの構成員や現在ヤクザとつきあいのある人物はインタビューできないことにプロデューサーとの間で合意していたと主張した。
翌月、訴訟の決着がつき、確定力のある決定として退けられた。すなわち、エーデルスタインはこの件について再び訴えることはできないということだ。番組は2014年に放映された。
「エーデルスタインはあの運転手については知っていたかもしれない。だが、他のヤクザは誰一人知らなかったと私は思う」とデイは言う。「あの本に書かれたことの半分は実際に起きたことではないだろう。彼の想像力の産物だ。フィクションだよ」
公正を期すために、エーデルスタインが命を狙われていたという主張を支持する人がいることも記事では触れられている。彼の知人で米国海兵隊の元大佐であり、モルガン・スタンレー日本支社のセキュリティ・アドバイザーを何年も務めたグラント・ニューシャムは、「後藤が彼を殺さなかったのは驚きだ。逃げおおせると思ったら後藤は実際にやっていただろうね」。
記事の公開後、デイのコメントについてエーデルスタインは彼のブログでこう反応している。「デイ氏は情報源を秘匿するという合意を破った。そのせいで訴訟が起きた」。
彼の弁護士はこう付け加えている。「ナショナル・ジオグラフィックの信用のために申し上げるが、訴訟が起こされ、交渉がデイ氏の手を離れた後、両者が納得できる大筋の合意に至るまで番組のプレミアを延期するなど、ナショナル・ジオグラフィックは責任ある態度で物事を処理した」
エーデルスタインも『Tokyo Vice』の中でこう書いている。「私に秘密を打ち明けてくれた人々を特に犯罪組織の報復から守るために出来事を改変したのだが、その理由を説明するのには非常に苦労した」。
(記事の要約ここまで)
最後に、このハリウッド・リポーター誌の記事が公開されたときの日本在住外国人のツイートをいくつかご紹介して、このブログ記事を締めくくることにしたい。
Wataru氏
彼らのヒーローであるエーデルスタインを批判したことで私は友人を失った。こうした形で彼が暴かれるのを見るのはとても素晴らしい。
I have lost friends because I dared to criticise their hero Adelstein. So good to see him getting exposed in this way. https://t.co/Zi7h34CnKu
— Wataru (Mastodon: @Tenkawa@mstdn.jp) (@yesthatwataru) 2022年4月30日
Electric Railfan氏
『Tokyo Vice』とその著者ジェイク・エーデルスタインのフィクションのいくつかを露 (あらわ) にするという点で、記者はいい仕事をした。本に描かれていることの多くがほぼ間違いなく実際に起きたことではないことを考えれば、どこから始めればいいか決めるのは難しかったはずだ。
The reporter has done a decent job exposing some of the fictions of Tokyo Vice and author Jake Adelstein. Given how many of the events described in the book almost certainly never happened, it would've been hard to know where to start.https://t.co/i2vtbytwDZ
— Electric Railfan (@WashletJP) 2022年4月30日
Dr. SkyNet, 2°氏
私は2010年代の前半に彼と東京で何度もあった。彼は自己宣伝に熱心な鼻もちならない40代の変わり者で、いつも大学生ぐらいの子たちとつるんでいるようだった。日本人は彼にとてもうんざりしていた。振り返ってみれば、彼は社会正義戦士の原型だったと思う。
I met Jake many times in Tokyo in the early 2010s and he was an insufferable, self-promoting, mid-40s weirdo who only seemed to hang with college kids. Japanese ppl thought he was embarrassingly cringe and looking back I realise he was a proto-sjw
— Dr. SkyNet, 2° 📡🛰🤯 (@DrSkyNetPhD) 2022年4月30日
Oliver Jia氏 (上のDr. SkyNet, 2°氏のツイートへのレスとして)
あなたの 言っていることは正しいと思う。そして、彼のでまかせの話を喜んで読んでいるのもおそらく大学生の子たちだろう。
Yep sounds about right. And college kids are probably his main audience of people entertained by his tall tales.
— Oliver Jia (オリバー・ジア) (@OliverJia1014) 2022年4月30日
以上